悼む人

『悼む人』というタイトルは、なんだか重いなと思った。本文の中で「悼む」という言葉が最初に登場するのは、プロローグの3頁めから4頁めにかけてである。
「『何をしているんですか』
思わず言葉をかけていました。まるで祈りをあげているような相手の姿に、動揺したのです。影が静かに立ち上がりました。若い男の人でした。前髪が目にかかる程度に髪を伸ばし、やや面長で、柔らかいもの問いたげな目をしていました。洗いざらしのTシャツに、膝に穴のあいたジーンズ、擦り切れたスニーカーをはき、足元に大きなリュックを置いています。
『いたませて、いただいていました』」
私はここで吹き出した。悼むという言葉をひらがなにすると、何ともカジュアルな印象である。しかも、ダジャレになってるじゃないか。私は唐突に「自分は最後のカウボーイだ」というようなセリフを言い放った『マディソン郡の橋』のロバート・キンケイドを思い出し、『悼む人』が、重いテーマを孕みつつもロマンスの香りに満ちたエンターテインメント小説であるに違いないと確信した。
物語の終盤で、私はもう一度笑った。都合のいい展開で盛り上がるドラマチックなシーンがあったのだ。予感は的中した。
☆
メディアを通じて、あるいは人に教えてもらうことで知った死者を訪ね、悼む旅を続けている青年、静人(しずと)。亡くなった人について<その人はどういう人に愛され、どういう人を愛し、どんなことで人に感謝されていたか>の3点のみを周囲の人に聞き、心に刻むことを心がけている。
静人はなぜそんなことをするのか? どこに泊まり何を食べているのか? 身勝手過ぎるんじゃないか? さまざまな疑問が頭をよぎるが、この小説は、それらを解明するミステリーである。主要登場人物は、エログロな記事を得意とする週刊誌の特派記者「薪野(まきの)」、静人の母親「巡子(じゅんこ)」、そして、通りすがりのワケあり女「倖世(ゆきよ)」の3人。つまり、人間の醜さを暴くプロの視点、彼をよく知る肉親の視点、彼をまったく知らない他人の視点という3つのアングルが用意されている。悼む人という奇妙なキャラクターを解き明かすには完璧な設定といえるだろう。
登場人物の多くは、鈍感でマイペースな自分探し野郎にしか見えない静人にいらだち、不信感を抱く。だが、静人の行為に理解ある人もいないことはない、という状況が積み重ねられるうちに、最終的にこの小説はどこへ行くのか。第一章で「なぜそんなことするの。宗教活動じゃないと言ったよね。じゃあ……」と言う蒔野に「ぼくは病気なんですよ」と答える静人。このセリフに引っ張られて私は最後まで読んだが、最大のミステリーは、この小説を読んで、自分の静人への気持ちはどう変わるのかということであった。
☆
小説の中盤で、薪野は巡子にぶしつけに言う。
「人々が彼を見る目は、はっきり言って厳しく、非難のほうが多いんです。馬鹿にされたように思う遺族もいるようです。そうと知れば、ご家族として、彼の旅を止めないはずはないんですが」
「彼の最終的な目的は何です。なぜ、いまのような生き方を選んだんです。親ならば把握なさってるはずでしょ。それとも、べつにどうでもいいですか。関係ない、と突き放されますか」
注目すべきは、その直後の描写だ。
「蒔野の細めた目が底光りした。そのとき、相手の内面に別の生きものが息づいているような錯覚を、巡子は抱いた。脂ぎった中年男の内側に、息をひそめてこちらをうかがい、答え方次第では食ってかかろうと、憎しみの目を冷たくとがらせている子供がいる……」
この後、小説のキモともいえる巡子のセリフが続くのだが、裏世界に通じるエログロな記者の中にすら「子供」が見える。これこそが著者の人間に対する視線ではないかと思う。誰もが、傷ついた子供であるということだ。
一方、静人と倖世の関係は、まるで聖フランチェスコとキアラのようだ。静人の理論武装は、旅の途中でさまざまな人の質問に答えるうちに強固になり、倖世との対話も聖人と弟子の様相を帯びる。だが静人は、聖フランチェスコのように親子の縁を切って巡礼の旅に出ているわけではないから、家族に迷惑をかけまくる。静人の名を音読みすれば「聖人」だが、実は、俗人の極みなのである。
そう、この小説には聖人なんて一人も出てこない。今の日本には、いろんなタイプの俗人がいるだけなのだ。では、そんな俗人ばかりの世の中では何が起きているのか。俗人は何を目的に生き、何ができるのか。とことん俗人に寄り添い、ヒーローになりえない「つまらない男」を主人公にし、最後のわずかな可能性のようなものを絞り出したこの小説は、非力だが、力強い。
☆
死が多く、めげるキャラクターも多いので、読んでいて疲れる。露悪的な描写で試されているような嫌悪感もある。だけど最後には、ロマンス小説のようなお楽しみもあるし、いくつかのいい風景を見ることができる。静人は家族を傷つけた落とし前をどうつけるのかという謎や、不信感を抱きつつ読み続けた読者が最後にどんな気分になるのかという最大の謎が解き明かされるまで、読むのをやめるべきではないだろう。
<無差別に悼む人>という特異なキャラクターは、<無差別に殺す人>が蔓延する世の中に、ごく自然に生まれてきた存在のように思われる。悼む人も殺す人も、どちらも病的であり、人がどちらに転ぶかは紙一重なのではないだろうか。どちらのキャラからも無縁であることができれば、それがいちばんいいに決まってる。世の中が平和な死ばかりなら、皆が身近なコミュニティー内で問題を解決できるなら、このようなパブリックな癒し小説が書かれる必要はないのだ。
週刊誌の扇情的な記事などをもとに、静人が悼みをおこなっているという俗っぽい設定は冴えている。私たちは日々、そのようなニュースに触れ、何かを感じ、被害者や加害者について自分勝手に都合のいい判断を下しているからだ。そんな私たちと「悼む人」の違いは、一体何だろう?
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
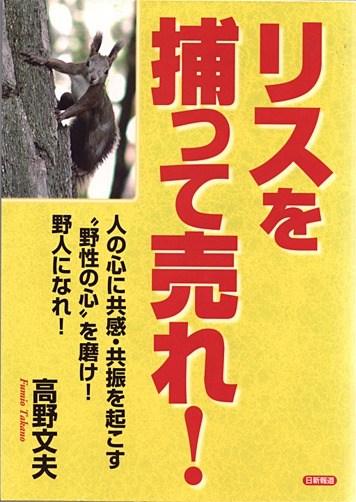
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















