「多くの祭り(フエト)のあとに」北條一浩

思えばありそうでなかった本である。確実に一つの時代を作り、「流通」業者と「文化」がクロスすることでどんなことが起こりうるかという、一種の壮大な実験場でもあった「セゾン文化」を概観する本となれば、これはいかにも「ありそう」だ。実際、『セゾン文化は何を夢みた』の巻末に「セゾン文化を追体験するためのブックガイド」が収録されているように、セゾングループの歴史やセゾン美術館、リブロについて語った本はすでに複数あり、なによりセゾングループ代表であった堤清二=辻井喬(注:堤清二は経営者としての本名、辻井喬は詩人・小説家としてのペンネーム)がなんらかの形でセゾンに触れた著作も少なくない。だから「なかった」のほうはいささか読み手の欲求を反映していて、ここで言いたいのは、客観的な通史や資料、カルチュラル・スタディーズ的な文化史ではなく、ある種の精神の風景と併走するような形でセゾンのセゾン(季節)を描写してくれるような本が「なかった」という意味である。
【セゾン系文化について書いていこう。セゾン系文化とは、セゾングループ、西武流通グループがやろうとした「文化事業」、およびそこから派生したもろもろを指す。あれはいったいなんだったのか。誰が、なんの目的ではじめて、なにを得、なにを失ったのか、考えていきたいと思う。うわべの気分としては二十代の自分のお骨拾いではあるけれど、心の奥のほうではいささか複雑だ。世代論や時代論としてではなく、企業と人とハイカルチャー/サブカルチャーの関係のようなものを振り返ってみたい。】
急いで紹介しなければならないが、著者の永江朗氏自身、「セゾン文化」出身者である。1981年に西武美術館にアルバイトとして雇われるところからキャリアがスタートし、アール・ヴィヴァン(洋美術書を揃えた書店)やカンカンポア(渋谷西武にあったその支店)などを経てフリーライターになった。読書術やインタビュー術の本をはじめ、本の現場やメディア論などを主なフィールドにしている書き手である。
「心の奥のほうではいささか複雑」と著者自ら書くように、本書は一見、明快な見取り図を取っているように見えて、どこか不透明なあいまいさを最後まで引き摺った本である。目次をみると「アール・ヴィヴァン」「リブロ」「セゾン美術館」「無印良品」「西武百貨店文化事業部」と章立てしてあり、なるほどセゾングループを構成したそれぞれの事業拠点ごとに追っていくのだな、ということがわかる。そしてアール・ヴィヴァンなら芦谷公昭、リブロは中村文孝、セゾン美術館は難波英夫と、それぞれ牽引車として深く係わった人々を訪ね、事業の発端から継続、その活動のオリジナリティ、困難などについて証言を丹念に収集していくことに多くの時間と労力を費やしたこともよくわかる。
ではなにが不透明であいまいかというと、「セゾン文化とは何だったのか?」を解き明かそうとした本であるにもかかわらず、その全体を俯瞰し、隅々まで掌握しようという意欲が希薄なように見えるということがまず一つ。それと、多くのセゾン関係者の証言を集めながらインタビュー集のような形はけっして取らず、個人(インタビューした相手)の性質がよく表れ、係わった仕事の質を簡潔に語ったごく少ない発言だけに絞っているのが不思議なのだ。
少し長くなるが大事な箇所を引用する。
【そこで私が連想するのは、柳宗悦の民芸運動であり、ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動だ。
二人ともユートピア思想をもっていた。生活が美しくなれば世の中がよくなるのだと信じていたし、そのためには
個人が日常生活について批判的な目を持つことが大切だと考えていた。日常生活の道具を素直に見るためには、と
きに名前が邪魔になる。名前が物を見る目を曇らせる。無印良品が匿名的であり続けるのは、消費者が名前ではな
く本質で商品を選ぶためのトレーニングとしてそれがあるからであり、その向こうには自立した個人としての消費
者、という夢があるからなのではないか。
「堤さんはあるとき、どんなに不景気になっても、生活は続いていくんですよね、とおっしゃったことがありま
す。物の力というのかな、そういうことを信じていないと、百貨店なんて怖くてやっていられないですよね。文化
はビジネスの付加価値なんかじゃない。そんなもんじゃないでしょう。人間は、より良い物がほしい、良い物を少
しでも手に取りやすく、ということが根底にあるんだと思います」
と小池は言う。】
これは「無印良品」の章のラスト部分で、小池とは小池一子氏のこと。自身もセゾンの一員であった永江氏の「考え」と小池氏の「言葉」が、あたかも霜降り肉の赤みと脂身の部分のように、渾然となって溶け合っている。上質の肉であればあるほど、赤身と脂身はよりきめ細かく融合し、互いにどちらが「地」でどちらが「文」であるかという区別をやめてしまう。
『セゾン文化は何を夢みた』は、繰りかえすが、「セゾン文化とは何だったのか?」を追求し、「企業と人とハイカルチャー/サブカルチャーの関係のようなものを振り返ってみた」試みである。カルチュラル・スタディーズではなく、研究書でもなく、「二十代のお骨拾い」とあるように著者自身の「マイ・バック・ページ」的な趣も漂わせながらそちらに雪崩れてくことにもどこか禁欲的で、あれでもなく、これでもなく、という本のたたずまいが、不透明なあいまいさの原因ではないかと思う。
そしてこのあいまいさがなんともリアルなのである。それは著者が最終章(出てくるのはもちろん、あの人だ)で、二つの名前のうちどちらも相手に向かって言えず、自分がすでにセゾンの人間でないにも係わらず「会長」と呼ぶしかないその不思議な居心地の悪さ(そこには少なからず甘美さもあると思う)と通じ合っているように思われる。
1981年、永江氏がセゾンの一員になった年、「一刻も早く東京の大学に行きたい」と悶々とする予備校生だった筆者はその翌年、念願の東京生活を果たし、夏休みに帰省してみると、西武百貨店宇都宮店の外壁スロープに、十数枚のウディ・アレンのポスターがズラリと貼られているのを見て、「????」と思った。近づいてよく見ると「おいしい生活。」と書いてある。なんで体言止めなのに「。」で止める? 東京に戻ると、当時付き合っていた一つ年上の彼女は栗本慎一郎ゼミに入り、なんだかだんだん人が変わったようになって、変わらないままの自分はあっさり捨てられ、彼女は西武百貨店船橋店に就職した。
詩というものを書いたりするようになり、池袋西武と渋谷西武にあった詩の専門書店(池袋が「ぽえむ・ぱろうる」、渋谷が「ぽると・ぱろうる」だ)にはしょっちゅう通って、同人誌も置いてもらっていた。自分の本が平積みになったこともある(!)。
そういう時代から徐々に上昇し、バブルとともに大きくもなり、同じくそれが弾けたのちに大きな痛手を蒙ったセゾン文化。「セゾン的なるもの」を憎む人にはある種のステレオタイプがあり、例えばそれは、企業が文化事業などという理想主義に走り、実は下半身はたまたまの好景気に支えられていたにすぎないから、景気が冷え込めばホラ、全部ダメになった、ざまあみろ、というようなものである。
しかしセゾン文化の中では、短い期間ではあったかもしれないが、生活と芸術が溶け合い、そこからなにか垣間見える可能性のようなものがあったことは確かだと思う。バブル絶頂、そしておそらくセゾン文化も絶頂期だったろう1987年に出た村上春樹の『ノルウェイの森』(とうとう映画まで作られてしまった)のエピグラフに、「多くの祭り(フエト)のために」という文言がある。68年5月に象徴されるような闘争の季節を指している(と思われる)この短いセンテンスを、私はずっと誤って「多くの祭り(フエト)のあとに」と記憶していた。甘かった。あれは祭りのあとのうつろさ、後遺症のような苦しみを描いた本だと思っていたけど、「ために」とあるから、実はもっと踏み込んだ本だったのだ。
そして『セゾン文化は何を夢みた』を読み終えたいま、もう一度ひっくり返して、これは「あとに」の地点に立っている本だと考えたい。企業が生活と芸術について何ができるかということを考えれば、いまは激戦のあとの荒地(それなりにフォトジェニックな)などではなく、もっとぜんぜん取り付く島のない更地だと思うからだ。「ために」書かれた『ノルウェイの森』が鎮魂(まだくすぶっているけど、どうか鎮火してください)の作業だとしたら、「あとに」書かれた『セゾン文化は何を夢みた』は、召喚(まだ灰になっていないなら、空気を送るから火が点いてくれ)の仕事である。
最後に、霜降り肉のメタファーは残念ながらむろん自前のものではなく、86年にパリのポンピドー・センター
でジャック・デリダと中上健次が対話した際、中上健次が「フランスのフォワグラ、あれは肝臓という解毒=排
除の器官だからダメで、赤みと脂身が渾然となった松坂牛のような日本文化の決定不能性には遠く及ばない」と
いう趣旨の発言をしたエピソードから取られている。
若い人は鼻で嗤うかもしれないが、ニューアカ全盛期に大学生活を送った人間の悪癖のようなもの、と告白し ておきます。
-
(画像はAmazonへのリンク) -
セゾン文化は何を夢みた
朝日新聞出版 国内
2010.09 版型:B6 ISBN:4022505389
価格:2,415円(税込)
堤清二(辻井喬)という特異な経営者を持ち、バブル期に日本企業としては異例の規模で広告や文化事業に資金を投入したセゾングループ。堤清二会長以下、紀国憲一文化事業部長、「無印良品」の誕生に携わった小池一子など、当時の関係者へのインタビューを基に「セゾン文化」が与えた影響を改めて問い直す。
書評書籍
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
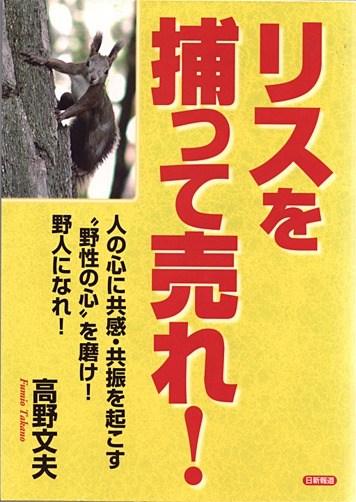
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















