〈ひとつの人影がくっきり浮かびあがった。同時に数千の人影も現れた。(中略)人影は、不快な気分をもよおす巨大な建物の壁から離れた。(中略)壁から切り出された人影は、他の姿に突き飛ばされてよろめいた。(中略)だが、このよろめきは見せかけにすぎなかった。ほんとうのところは、労働から睡眠への、辛さから退屈への、苦痛から死への最短ルートだったのだ〉
謎めいた書き出しとともに現れる〈人影〉の持ち主の名は、エティエンヌ。妻子持ちで、2階が未完成のヘンテコな一戸建てに住んでいる、うだつが上がらない会社員だ。なぜ彼が登場人物として、浮かび上がってきたのか?それは、観察者ピエールの目に留まったから。身分も出自もわからないこの男は、物語の語り手でもなければ狂言回しとも違う。ただ、彼がエティエンヌを観察することで物語は始まる。主要な登場人物として話に介入もするけれど、それによってどんな展開になるかまでは、把握していない。でも自分が〈作中人物〉だと自覚もしているという、何とも不思議な役回りなのだ。
『文体練習』などの実験的な作品で知られ、潜在文学工房(ウリポ)の発起人の一人でもあったフランスの作家レーモン・クノー。昨年秋に刊行が開始された、水声社「レーモン・クノー・コレクション」の最新刊にして処女作でもある本書について、読みにくい難解な小説をイメージするかもしれないけれど、決してそんなことはない。
手探りの状態で始まった物語は、ピエールの乗ったタクシーがエティエンヌを轢きそうになった事故を境に、一つの筋が見えてくる。エティエンヌは事故が縁で知り合いとなったピエールを誘って、郊外のフライドポテト屋へ向かう。そこで出会った古物商トープ爺さんの家へ品物を見に行った二人だが、掘り出し物はなく店に戻ることにする。その帰り道、トープ爺さんの家の青く塗られた戸の後ろには、金が隠されているかもしれないという雑談をする。すると話が漏れて、詮索好きで欲深いクロッシュ夫人に伝わり、思わぬ騒動に発展してしまう。
さまざまな偶然や勘違いが重なることで物語は進んでいくけれど、伏線が読者に提示されているので、筋が頭に入ってきやすい。そこへクノーの作品に欠かせない要素である笑い—たとえば、「小人主義」=ナニスムを、「自慰」=オナニスムと取り違えるような言葉遊び。たとえば、喧嘩を実況しているはずがいつのまにか殺し合いを実況しているというような寸劇の数々—が加わることで文章にリズムが生まれて、読みやすく飽きがこない。
登場人物も個性派揃い。前述の人々に加え、エティエンヌの妻に恋する失業中の音楽家ナルサンス。エティエンヌの義理の息子で生意気な少年タオ。弱みに付け込んで人に寄生して生きる小人ベベなど、一癖も二癖もある人間ばかり。さらには、当時1930年代のフランスを暗示する戦争の影や、登場人物の漏らす内省的な呟きが物語に陰影を加える。
作品に盛り込まれている多様なモチーフや手法には、何らかの意味が込められているはずである。だけども、ひとつひとつについて考えれば考えるほど、その全貌がぼやけてしまう印象がある。本書には全体を通して、存在することの意味など哲学的な問いかけも見られる。ところが、これを読解の突破口にしようとしても、結局は作者によってはぐらかされてしまう。〈これから神さまの話なんかをするつもりじゃないだろうね?〉と登場人物に言わせて哲学問答を打ち切り、真理に手が届きそうな途中で話をリセットしてしまうのだ。そしてまた、新たな企みの元に作られた作品へと読み手を誘っていく。
そんな作者の足跡を、この水声社のコレクションによって辿らない手はない。クノーの作品には、いつまでも答えの出ない世界を生きる愉しさがある。
-

(画像はAmazonへのリンク) -
『はまむぎ』
水声社 [小説] 海外
2012.06 版型:単行本 ISBN:4891768614
価格:3,360円(税込)
青年時代をシュルレアリスムの激動のなかに過ごしたクノーは、本書によって独自の原理にもとづく創意あふれる散文世界へ踏み込んだ。現代小説の新しい形式を用意した先駆的作品。
書評書籍
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
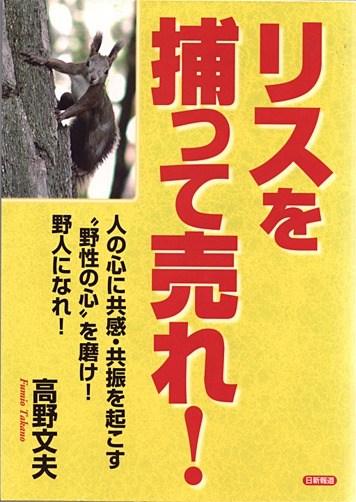
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。

















