告白

凄い新人が現れたものだ。これがデビュー作とは! ちょっと信じられないほどの完成度ではないか。話題の湊かなえ『告白』である。
『聖職者』という作品で第29回小説推理新人賞を受賞した湊かなえであるが、同作品は『告白』の第一章として冒頭に収められており、以降の全六作はすべて巧みに連結され、ひとつの物語を形成している。なにによって連結されているか? 憎悪によってである。
それにしても、なんという異常な構成なのか。冒頭の『聖職者』を読んですぐにそれに気づかされる。中学校の終業式の日。一年生のあるクラスでの、女性の教師の生徒たちへの退職の挨拶。まさにモノローグ以外のなにものでもないこの教師の語りだけで、『聖職者』は構成されているのだ。
正確には、モノローグという形式自体は異常ではない。ただし一切の前提・了解もなく、女教師が恐ろしい話を唐突にしかもよどみなく話し始めるのだ。この思いよらぬ展開を異常といわずしてなんというべきか。そしてその話が「愛娘の愛美は、このクラスの生徒に殺されたのだ」という告白に至り、異常性は早くもピークに達する。クラスも凍りついたが、読んでいるこちらの背中にも電気が走る。
さらに本文四十七頁のこの『聖職者』を読むだけで、異常なだけではない、実に緻密な構成であるということにも気づかされる。
激しく巨大な憎悪をちらつかせながら、犯人を次第に特定し追い詰めてゆく教師・森口悠子の、低温質の大きなトカゲが高度な知能を得たかのようか、恐るべき周到な語り口。当初、散漫なパーツにすぎないと思われていた話は、瞬く間に事件の全貌の構成パーツとして重要な役割を担い、読者は悠子の話に釘付けとなる。やがて、驚くべき告白…。
戦慄の四十七頁。第一ラウンドでいきなりKOを食らったような気分だ。作者・湊かなえは放送作家であるようだが、相当に推敲を重ねてこの『聖職者』を完成させたのではないかと推察する。凄い集中力のエネルギーがこの『聖職者』に満ちているのだ。
次いで『殉教者』。
いきなりまた唸らされる。今度はそのクラスの生徒、北原美月のモノローグだ。
なんと大胆な。そう、この後も人が入れ替わってモノローグが続いていくのだ。
そして、悠子が去った後の凄惨なできごとが語られる。犯人の側からの事件の真相が語られる。やがて最終章、わずか本文十三頁の『伝導者』において、憎悪のマグマは大爆発を起こす。
驚くべき大胆かつ緻密な構成に、読む者はみな衝撃を受けるだろう。
ただそれだけではない。『告白』ではいまの日本社会が抱える複数の問題が、浮き彫りにされている。
中学校一年生、十三歳の犯罪であるというところが、まずキーとなる。刑事罰対象年齢は十四歳からであるからだ。ここに悠子が自ら手を下した理由がある。そしてそれは同時に作者・湊かなえの問題提起でもある。
つまり、肝心の真相究明までは至らない報道への不信。犯人である少年少女の自己陶酔、さらにはアイドル化。そして、数年後に約束されているかのような社会復帰。被害者の親の、まさに行き場がまったくない怒り…。
学校に目を転じれば、クラス内では声の大きい生徒に雪崩を打ったように従わざるを得ない恐怖と、その多数派に属せない生徒へのいじめ。あまりに思慮が足りない、先生とはとても呼べない幼い教師の存在。外に漏れるまでは社会に問題をオープンにしない学校の隠蔽体質。家庭では子の心のうちに思いをめぐらすことのできない親、子を捨てることのできる親。
それらの根底にあるのは、もはや社会に定着してしまった倫理観の崩壊である。
湊かなえの現状認識であるさまざまな関係性での不信が大きな憎悪となって渦を巻き、ここ物語を支えている。それは紛れもない現実でもある。凶悪な少年犯罪自体はもはや珍しくないのがその証しだ。『告白』で描かれているおぞましい憎悪の連鎖が現実のものとなっても、もはやなんの不思議もない。そしてこれだけのデビュー作を上梓した湊かなえも、もはや恐るべき存在だ。
(刑事罰対象年齢に達しない少年犯罪に対する作者の問題提起は真っ当であるが、設定からの必然である十三・四歳の中学生のモノローグには少し違和感が残る。彼・彼女らの、自らの気持ちや行動を語るモノローグが実に能弁なのだ。作者はあえて、本来はまだ残っている幼さに目を瞑ったのだろう。そのために彼・彼女らの心の動きは整理がついてわかりやすい。でも整理が行き届いた分、リアリティが少しだけ損なわれたのではないか、というのが唯一の不満です)。
新着情報
-

- 2013/08/16[新着書評]
『きことわ』朝吹真理子
評者:千三屋
-

- 2013/08/15[新着書評]
『テルマエ・ロマエⅥ』ヤマザキマリ/「1~3巻は大傑作、4~6巻は残念な出来」
評者:新藤純子
-

- 2013/06/19[新着書評]
『高円寺 古本酒場ものがたり』狩野俊
評者:千三屋

- 2013/05/12[新着書評]
『フィフティ・シェイズ・ダーカー(上・下)』ELジェイムズ
評者:日向郁

- 2013/04/04[新着書評]
『クラウド・アトラス』デイヴィッド・ミッチェル
評者:千三屋

- 2013/02/18[新着書評]
『はぶらし』近藤史恵
評者:日向郁

- 2013/01/31[新着書評]
『知的唯仏論』宮崎哲弥・呉智英
評者:千三屋

- 2013/01/18[新着書評]
『秋田寛のグラフィックデザイン』アキタ・デザイン・カン
評者:千三屋

- 2013/01/17[新着書評]
『空白を満たしなさい』平野啓一郎
評者:長坂陽子

- 2013/01/15[新着書評]
『箱根駅伝を歩く』泉麻人
評者:千三屋

- 2013/01/11[新着書評]
『世界が終わるわけではなく』ケイト・アトキンソン
評者:藤井勉

- 2012/12/19[新着書評]
『デザインの本の本』秋田寛
評者:千三屋

- 2012/11/28[新着書評]
『ニール・ヤング自伝I』ニール・ヤング
評者:藤井勉

- 2012/11/22[新着書評]
『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』友利昴
評者:新藤純子

- 2012/11/21[新着書評]
『私にふさわしいホテル』柚木麻子
評者:長坂陽子

- 2012/11/15[新着書評]
『格差と序列の心理学 平等主義のパラドクス』池上知子
評者:新藤純子
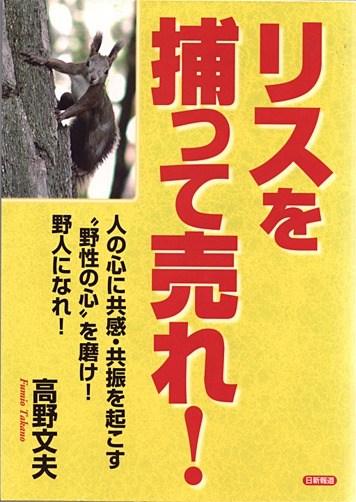
- 2012/11/09[イベントレポ]
兼業古本屋のできるまで。とみさわさん、なにをやってんすか

- 2012/11/08[新着書評]
『機龍警察 暗黒市場』月村了衛
評者:大谷暁生

- 2012/11/02[新着書評]
『なしくずしの死』L-F・セリーヌ
評者:藤田祥平

- 2012/10/31[新着書評]
『エコー・メイカー』リチャード・パワーズ
評者:藤井勉

- 2012/10/30[新着書評]
『文体練習』レーモン・クノー
評者:藤田祥平

- 2012/10/25[新着書評]
『生きのびるための建築』石山修武
評者:千三屋

- 2012/10/24[新着書評]
『占領都市 TOKYO YEAR ZERO Ⅱ』デイヴィッド・ピース
評者:大谷暁生

- 2012/10/19[新着書評]
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』ランディ・パウシュ、ジェフリー・ザスロー
評者:日向郁

- 2012/10/18[新着書評]
『イタリア人と日本人、どっちがバカ?』ファブリツィオ・グラッセッリ
評者:相川藍

- 2012/10/17[イベントレポ]
ミステリー酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場Part1

- 2012/10/16[イベントレポ]
ブックレビューLIVE:杉江VS米光のどっちが売れるか!?

- 2012/10/15[イベントレポ]
ミステリ酒場スペシャル ローレンス・ブロック酒場三連発 PART2~泥棒バーニー、殺し屋ケラー編&ブロックおもてなし対策会議~

- 2012/10/15[新着書評]
『犬とハモニカ』江國香織
評者:長坂陽子

- 2012/10/10[新着書評]
『Papa told me cocohana ver.1 丘は花でいっぱい』榛野なな恵
評者:千三屋

- 2012/10/08[イベントレポ]
“その日”が来てからでは遅すぎる! あなたの知らないお葬式のすべて?ボッタクリの秘密から納得のエコ葬儀プランまで

- 2012/10/03[新着書評]
『青い脂』ウラジーミル・ソローキン
評者:藤井勉

- 2012/10/02[イベントレポ]
松本尚久さん、落語の楽しみ方を教えてください!

- 2012/10/01[新着書評]
『ヴァンパイア』岩井俊二
評者:長坂陽子

- 2012/09/25[新着書評]
『鬼談百景』小野不由美
評者:挟名紅治

- 2012/09/24[新着書評]
『ここは退屈迎えに来て』山内マリコ
評者:長坂陽子

- 2012/09/18[新着書評]
『最初の人間』アルベール・カミュ
評者:新藤純子

- 2012/09/14[新着書評]
『その日東京駅五時二十五分発』西川美和
評者:相川藍

- 2012/09/13[新着書評]
『無分別』オラシオ・カステジャーノス・モヤ
評者:藤井勉

- 2012/09/12[新着書評]
『鷲たちの盟約』(上下)アラン・グレン
評者:大谷暁生

- 2012/09/11[新着書評]
『ラブ・イズ・ア・ミックステープ』ロブ・シェフィールド
評者:日向郁

- 2012/09/10[新着書評]
『嵐のピクニック』本谷有希子
評者:長坂陽子

- 2012/09/07[新着書評]
『本当の経済の話をしよう』若田部昌澄、栗原裕一郎
評者:藤井勉

- 2012/09/05[新着書評]
『ひらいて』綿矢りさ
評者:長坂陽子

- 2012/09/04[新着書評]
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』フリードリヒ・デュレンマット
評者:藤井勉

- 2012/09/03[新着書評]
『かくも水深き不在』竹本健治
評者:蔓葉信博

- 2012/08/31[新着書評]
『わたしが眠りにつく前に』SJ・ワトソン
評者:長坂陽子

- 2012/08/28[新着書評]
『芸術実行犯』Chim↑Pom(チン↑ポム)
評者:相川藍

- 2012/08/27[新着書評]
『ぼくは勉強ができない』山田詠美
評者:姉崎あきか

- 2012/08/16[新着書評]
『オカルト 現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ』森達也
評者:長坂陽子

- 2012/08/10[新着書評]
『セックスなんか興味ない』きづきあきら サトウナンキ
評者:大谷暁生

- 2012/08/08[新着書評]
『深い疵』ネレ・ノイハウス
評者:挟名紅治

- 2012/08/07[新着書評]
【連載】 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第4回 小林直樹『ソーシャルリスク』 評者:蔓葉信博

- 2012/08/03[新着書評]
『はまむぎ』レーモン・クノー
評者:藤井勉

- 2012/08/02[新着書評]
『清須会議』三谷幸喜
評者:千三屋

- 2012/07/31[新着書評]
『岡崎京子の仕事集』岡崎京子(著)増渕俊之(編)
評者:相川藍

- 2012/07/28[新着書評]
『ことばの食卓』武田百合子
評者:杉江松恋

- 2012/07/18[新着書評]
『図説 死因百科』マイケル・ラルゴ
評者:大谷暁生

- 2012/07/13[新着書評]
『最果てアーケード』
小川洋子
評者:長坂陽子

- 2012/07/12[新着書評]
『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』橋爪大三郎
評者:千三屋

- 2012/07/05[新着書評]
『少年は残酷な弓を射る』(上・下)
ライオネル・シュライヴァー
評者:長坂陽子

- 2012/07/04[新着書評]
『未解決事件 グリコ・森永事件~捜査員300人の証言』NHKスペシャル取材班
評者:挟名紅治

- 2012/07/02[新着書評]
『女が嘘をつくとき』リュドミラ・ウリツカヤ
評者:藤井勉

- 2012/06/29[新着書評]
連載 蔓葉信博「週末、たまにはビジネス書を」
第3回 三浦展『第四の消費』 蔓葉信博

- 2012/06/27[新着書評]
『シフォン・リボン・シフォン』近藤史恵
評者:相川藍

- 2012/06/26[新着書評]
『湿地』アーナルデュル・インドリダソン
大谷暁生

- 2012/06/20[新着書評]
『彼女の存在、その破片』野中柊
長坂陽子

- 2012/06/15[新着書評]
『新人警官の掟』フェイ・ケラーマン
日向郁

- 2012/06/14[新着書評]
『俳優と超人形』ゴードン・クレイグ
千三屋

- 2012/06/13[新着書評]
『毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記』北原みのり
長坂陽子

- 2012/06/12[新着書評]
『WOMBS』白井弓子
大谷暁生

- 2012/06/11[新着書評]
『21世紀の世界文学30冊を読む』都甲幸治
藤井勉

- 2012/06/08[新着書評]
『愛について』白岩玄
評者:相川藍

- 2012/06/06[新着書評]
『柔らかな犀の角ー山崎努の読書日記』山崎努
挟名紅治

- 2012/06/04[新着書評]
『夜をぶっとばせ』井上荒野
長坂陽子

- 2012/06/01[新着書評]
「七夜物語』川上弘美
長坂陽子

- 2012/05/23[新着書評]
「ピントがボケる音 OUT OF FOCUS, OUT OF SOUND』安田兼一
藤井勉

- 2012/05/21[新着書評]
「飼い慣らすことのできない幻獣たち」
『幻獣辞典』ホルヘ・ルイス・ボルヘス
藤田祥平

- 2012/05/16[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第18回」
「その名は自己満足」 長坂陽子

- 2012/03/30[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第17回」
「そのプライドが邪魔をする」 長坂陽子

- 2012/02/28[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第16回」
「恋のリスクマネジメント」 長坂陽子

- 2012/02/15[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第15回」
「非華奢女子の生きる道」 長坂陽子

- 2012/02/02[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第14回」
「パターン破りの効用」 長坂陽子

- 2012/01/31[新着書評]
『最高に美しい住宅をつくる方法』彦根明
評者:相川藍

- 2012/01/20[新着書評]
『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ
評者:藤井勉

- 2012/01/17[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第13回」
胸だけ見ててもモテ期はこない 長坂陽子

- 2012/01/11[新着書評]
連載「長坂陽子 ロマンスの神様願いを叶えて第12回」
「恋で美しくなる」は本当か 長坂陽子

- 2012/01/10[新着書評]
「旧式のプライバシー」
『大阪の宿』水上滝太郎
藤田祥平
Internet Explorerをご利用の場合はバージョン6以上でご覧ください。
















